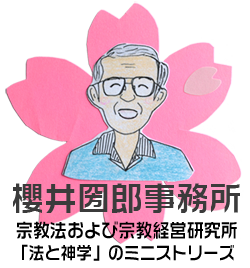<危機管理を担う案山子>
(ロシア連邦ウラジミール州スズダリ市にて)
・
[目 次]
0 危機意識
1 予兆の無視
2 「軽く終わる」という期待
3 「元に戻る」という思い込み
Ⅰ コーポレート・ガバナンス
1 求められるコーポレート・ガバナンス
2 「コンプライアンス(規範倫理)」
3 「ディスクロージャー(情報開示)」
4 「アカウンタビリティ(説明責任)」
5 内部統制・組織管理
6 内部通報・公益通報
7 本人確認
Ⅱ リスク・マネジメント(RM)
1 リスクとマネジメント
2 RMのルール
3 危機管理
4 不祥事対策
5 クレーマー対策
6 「多数リスク」「少数リスク」
Ⅲ 犯罪被害者の支援
1 公判手続の傍聴
2 公判記録の閲覧・謄写
3 犯罪被害者の証人尋問
4 被害者参加
5 刑事裁判における民事上の和解
6 刑事裁判における損害賠償請求
Ⅳ ストカー対策
1 「ストーカー行為」都は
2 「つきまとい等」とは
3 「つきまとい等の行為」とは
4 つきまとい等の禁止
5 警察署長の警告
6 公安委員会の禁止命令
7 ストーカー対象者の情報提供の禁止
Ⅴ 暴力団の排除
1 根拠法令
2 定義
3 禁止行為
4 暴力団排除活動
Ⅵ 幼児虐待・児童虐待への対応
1 幼児虐待・児童虐待の発見
2 虐待されている幼児・児童虐待への対応
3 虐待している親などへの対応
Ⅶ 秘密の保持
1 信仰の秘密・宗教の秘密
2 プライバシーの保護
3 個人情報の保護
Ⅷ ハラスメントの防止
1 ハラスメントとは
2 セクシャル・ハラスメント(セクハラ)
3 パワー・ハラスメント(パワハラ)
4 宗教ハラスメント
5 ハラスメントの防止
6 「逆ハラスメント」
Ⅷ-2 信徒からのハラスメント
1 ハラスメントとは
2 セクシャル・ハラスメント(セクハラ)
3
Ⅸ 「宗教詐欺」の被害防止
1 宗教団体などを狙った詐欺
2 宗教詐欺にあわないために
3 宗教詐欺にあったら
Ⅹ クリーンハンドの原則
1 「盗人猛々しい」
2 「クリーンハンドの原則」
3
Ⅺ リスクと経営
1 リスク経営
2 リスク回避
3 リスク回復
Ⅻ リスクと事業継続計画(BCP)
1 自然災害の増加・巨大化と災害リスク対応
2 高齢化・後継者問題と経営リスク対応
3 事業継続強化計画(事業強靭化)
XⅢ 防災・災害対策・被災者支援
1 防災と災対
2 防災
3 災対
4 電子情報の防災
5 被災者支援
XⅣ 防犯カメラ・監視カメラ
1 防犯カメラ・監視カメラとは
2 防犯カメラの設置
XⅤ 感染症の防疫対策
1 感染症とは
2 防疫対策
3 費用負担
4 特別措置
5 緊急事態措置
XVI 危機管理規程
1 危機管理規程とは
2 危機管理協定
3 危機管理規程
XVII HACCP(危害分析重要管理ポイント)
1 食品の危機管理
2 HACCP7原則
3 HACCP5手順
XVIII
XIX
XX
[キーワード]
「コンプライアンス」「アカウンタビリティ」「ディスクロージー」「C S R(社会的責任)」「内部統制」「公益通報(内部通報)」「本人確認」「秘密保持」「個人情報」「犯罪被害者」「ストーカー」「告訴告発」「刑事裁判」「セクハラ(セクシャルハラスメント)」「パワハラ(パワーハラスメント)」「宗教ハラスメント」「逆ハラスメント」「暴力団」「幼児虐待」「児童虐待」「クレーマー」「防災」「災対(災害対策)」「防犯カメラ」「監視カメラ」「感染症」「緊急事態宣言」「盗人猛々しい」「クリーンハンドの原則」
・
・
・
0 危機意識
1 危機意識の欠如
⑴ 最大の危機
・ ㋑ 人間社会における「最大の危機」は「危機意識の欠如」です。
・ ㋺ その点は、国家の存続、企業の経営、事業の継続、家庭の問題など、あらゆる問題に共通します。
・ ㋩ もちろん、「宗教の存続」「宗教団体の興亡」にも共通します。
⑵ 危機意識の欠如の結果
・ ㋑ 国家では、
・ 予兆を見逃し、安穏と対応した結果、大きな戦争に発展し、国家存亡の危機に遭遇するおそれがあります。
・ ㋺ 企業では、
・ 危機意識のない、平穏無事の経営体質では、常に、経営が逼迫し、倒産の危機に遭遇する可能性があります。
・ ㋩ 個人では、
・ 何も考えずに、政府や企業の言うままに何もしないでいては、生命・身体・財産・家庭・家族の危機に遭遇するかもしれません。
2 3つの危機意識の欠如
・ ㋑ 「危機意識の欠如」は、次の3つの段階で生じます。
・ ① 「予兆の無視」
・ ② 「軽く終わる」という期待
・ ③ 「元に戻る」という思い込み
・ ㋺ 「今の状態」を存続させ、継続させたいという人間の思いに起因します。
・ ㋩ これらは、「時」「時間」に関わる問題であり、「時間下」にある人間には理解が困難・不可能な問題であることから、それを否定し、無視する傾向が生まれています。
3 予兆の無視
・ ㋑ 「予兆の無視」は、最初の段階です。
・ ㋺ 大きな事件・事故・現象・感染・災害・事変・戦争などには、それなりの予兆があります。
・ ㋩ 無神論者・無宗教者・唯物論者は、予兆を見て、これを無視する傾向にあります。
・ ㋥ 「予兆の無視」は、その先の判断や対処・対応に遅れを生じます。
・ ㋭ 判断・対応・対処の遅れは、決定的なダメージを生む可能性があります。
・ ㋬ 宗教者は、世界が神によって支配されているという意識から、「神の声」としての予兆に意を配ります。
・ ㋣ 何も起こらなければ問題ないことですから、常に、気を配り、万が一の対応策を講じておくことが必要です。
・ ㋠ 対策を練らなくても、意識をするだけでも、ダメージを抑えることが可能です。
4 「軽く終わる」という期待
・ ㋑ 第2段階は、少し、問題が発生しても、「軽く終わるだろう」という楽観視です。
・ ㋺ 「軽く終わる」という期待ともいえます。
・ ㋩ その結果、「軽く終わる」という見解にのみ同意し、逆の見解を無視する傾向が生まれます。
・ ㋥ それによって、対応策が遅れ、対処が困難になる傾向があります。
・ ㋭ 企業であれば、無対処のまま、在庫物品の過不足、従業員の余剰や不足、資金ショートや金余り、取引の急増急減などに至り、事業存続の困難、企業の倒産に陥ってしまう恐れがあります。
・ ㋬ 宗教団体にあっても同様です。真摯に「神の声」を聞き、常に「最悪の状態」を想起して、対応することが求められます。
5 「元に戻る」という思い込み
・ ㋑ 第3段階は、この先、問題が解決すれば、「以前と同様の状態に回復する」と考え、「元に戻るはず」と思い込むことです。
・ ㋺ それは、将来計画を平坦な路面で考えることであり、時間下にあり、未来の見えない人間の傾向です。
・ ㋩ 天地創造以来の人間の歴史を考えれば、予想できない大きな変化を重ねてきました。
・ ㋥ 誰もが知っている「ノアの洪水」は決定的です。人間の寿命も約1000年から約100年(120年)に短縮されるほどの、地球環境の根本的な変化を生じています。
・ ㋭ この1000年の世界の歴史、この数百年の日本の歴史、明治以来の近代日本の歴史、終戦後の現代日本の歴史、この数十年の世界の動きを考えてみても同様です。
・ ㋬ 交通であれば、徒歩から、馬、馬車、牛車、汽車、電車、自動車に、新幹線に、手漕ぎ船から帆船、汽船に、飛行機に。通信であれば、狼煙、飛脚、郵便、電信、電話、無線電話、携帯電話、スマートフォン、インターネットに。元には戻りません。
・ ㋣ 宗教者は、時間を超える「永遠の神」の支配・統治・計画・御意を汲み取ろうとし、理解しようとし、それに沿って身を律し、生きようとします。
・

Ⅰ コーポレート・ガバナンス
1 求められるコーポレート・ガバナンス
⑴ 株主への責任
① 「コーポレート・ガバナンス」とは、「企業統治」という意味です。
② 多数の株主の投資によって経営される株式会社について、責任ある経営を求めて生まれた論理です。
⑵ 社会への責任
① 株主だけではなく、取引先や顧客・消費者の利益のためにも展開されます。
② 地域住民や一般市民との関係でも求められています。
⑶ 公益団体の責任
① 営利企業の経営責任だけではなく、法人や団体の経営全般に及んでいます。
② 社会の負託を受けて活動する大学や公共施設、社会福祉施設、公益法人にも及んでいます。
⑷ 宗教団体のガバナンス
① 「宗教」は、㋑「国家を超える」活動であり、国家の規制は受けません(信教の自由)が、㋺「宗教団体」には、衆目が注がれ、多数の人々の期待と信頼が向けられています。
② したがって、当然に、㋑「宗教団体」「宗教法人」の運営には、多大な責任が求められ、㋺「宗教団体」「宗教法人」には、「コーポレート・ガバナンス」が求められます。
③ 現在社会においては、㋑「コーポレート・ガバナンスの充足度」が、社会的評価の対象となっており、㋺それが、社会的存在としての宗教団体・宗教法人の価値を定めるといえます。
④ 宗教団体・宗教法人には、㋑宗教団体・宗教法人の特殊性を顧慮した、ガバナンスが求められます。㋺それは、一般企業や一般法人のルールがそのまま通用するわけではなく、㋩一般企業や一般法人と同じ次元のルールでは、足りないと考えるべきであり、㋥高度な次元での、特別な「宗教団体ガバナンス」が適用されるべきです。
⑸ 「宗教団体ガバナンス」の基本
㋑ 「宗教団体ガバナンス」の基本は、①「コンプライアンス」、②「ディスクロージャー」、③「アカウンタビリティ」の3点です。
㋺ 「基本」とは、①基礎であり、最低線という意味であり、②基本ガバナンスで満足していては事足りませんし、③更に充実し、更にレベルの高いガバナンスを実現していくべきです。
2 「コンプライアンス(規範倫理)」
⑴ 「規範」とは
㋑ 「規範」とは、①あらかじめ、②文字で書かれ、③公示された、ルールをいいます。法、法律、法令、規則、規範、基準、ルールなど「客観的な基準」をいいます。
㋺ 「規範」には、①国家の法律・命令・条例・規則などだけでなく、②団体の内部規則、連合団体の取極め、関連団体との協定、取引先との契約約款などもあり、③あらゆる客観的な基準が含まれています。
㋩ 「宗教団体」の場合には、①世俗団体とは異なり、②人間の定めた規範だけではなく、③神仏の意思およびその具現としての経典・聖典・聖書・由緒・伝承などがあり、④それらが「最高規範」として存在しています。⑤それらを遵守するのが「宗教団体」です。
⑵ 「日本人の法嫌い」
㋑ 西欧の社会は、①規範にしたがって物事を考え、行動をし、事態を吟味し、評価します。②それを、「法治主義」「規範倫理」といいます。
㋺ 中国・韓国・日本などの東洋の社会では、①統治者・指導者・指揮者などの才覚にしたがって諸事を行う伝統があります。②「人治主義」「徳治主義」が是とされる傾向があります。
㋩ そのため、①「主観的な行動」が、「暖かい」「愛がある」などと評価される一方で、②「客観的な基準」が、「冷たい」「情がない」などと嫌われる傾向があります。
㋥ そこには、①「規範がない方が良い」という感覚があります。②いわゆる「日本人の法嫌い」です。
⑶ 形式主義と実質主義
㋑ 西欧では、①「規範」は、本来の趣旨・目的に適合するように適用されるべきと考えられますから、②具体的な事案に対応して、規範の意味を解釈することが必要とされ、③文字に拘泥せず、実質的に、正しく適用しようとします(実質的正義・実質主義)。
㋺ 東洋・日本では、①規範は文字通りに厳格に適用されるべきであると考えられ、②解釈を厭う傾向にあります(形式的正義・形式主義)。
⑷ 「法令遵守」
㋑ 日本の企業や法人団体では、①コーポレート・ガバナンスという欧米の理論を適用するのに意識の差があり、②特に意図し、意識的に行うということではありませんが、結果的に現れて、③結果的に、日本的な形態となっています。
㋺ その一つが、①「コンプライアンス」を「法令遵守」と言うことであり、②「法令」と言うことによって、規範を国家の法令のみに限定し、③それも強制力のある条項に限ってしまいます。
㋩ そして、①「遵守」を「文字通りに守る」こととすることによって、②強制力のある法令条項「〇〇してはならない」に抵触しないように、消極的になってしまい、③強制力のない法令条項は「強制力がないから」という理由で、無視・軽視されてしまい、④本来、法令の求めていることを実現しようとする「積極的な姿勢」が欠けて、⑤「表面的に守ること」「違反しない形式を整えること」で過ごされてきた傾向にあります。
⑸ 「規範倫理」
㋑ 小職は、①「コンプライアンス」を「規範遵守」としたいのを、誤解を恐れて、抑えており、②そして、日本人の法意識を考え、「規範倫理」と言っています。
㋺ ①「規範遵守」なら、形式的に規範通りに履行すること(形式主義)で通用しますが、②「規範倫理」となれば、規範の意味すること、規範の目的とすることを実現すること(実質主義)が求められるからです。
⑹ 宗教主宰者の特則
㋑ 宗教団体にも、①規範倫理は適用されますが、②世俗の団体とは根本的に異なる点があり、顧慮が必要です。
㋺ 宗教主宰者は、①教祖、貫主、管長、座主、教皇、総裁、統理、司教、神官、宮司、住職、牧師、司祭など、②神仏の代理人やその意思の具現者であり、③信仰の対象・崇敬の対象でもあり、④宗教の教義において、その言動が信仰上の規範とされる場合もありますから、⑤その限度において、人間の定めた規範に従う存在ではありません。
㋩ その限りにおいて、宗教主宰者には規範倫理は非適用と思われがちが、そうではありません。
㋥ 宗教主宰者は、①自分自身が「規範の規範」であり、②より高次の神仏の規範に従う者であり、③高次の規範倫理を実践する者です。
㋭ したがって、規範を否み、規範に反し、規範を曲げ、規範に矛盾する言動がありはずはありません。
㋬ 宗教主宰者こそ、規範倫理の具現者であるはずです。
3 「ディスクロージャー(情報開示)」
⑴ 社会的な存在
㋑ 企業も、諸団体も、①社会の負託を受け、社会の協力を得て、社会の中に存在し、活動しているですが、②その運営や活動の実態が、外部の社会には分からないままでした。
㋺ そこから、①「有害な物を造っているのでは?」「悪いことをしているのでは?」などと疑問が生れ、②社会に不安を与え、社会の不信を招くことになりました。
㋩ 社会との良好な関係を保つために、①社会に向かって、企業や団体の目的・事業内容などを明らかにすることが必要とされ、②目的・事業、組織・構成、取引先・関連団体、主な活動内容、収支状況などを社会的に明らかにすることが求められています。
⑵ 「ディスクロージャー(情報開示)」
㋑ 「ディスクロージャー(情報開示)」とは、①特定の活動や内容などに関して求めがあった場合に、該当の情報を開示することであり、②可能な限り、その事実を明確・明瞭にする情報を開示することが求められます。
㋺ 「情報開示」といっても、①「全ての情報」を開示しなければならないということではありませんし、②当然に、「企業の秘密」もあり、「秘密の保持」も必要です。
㋩ 当然に、①「秘匿しなければならない情報」「保護しなければならない情報」もありますが、②その点についても、明確・明瞭なルールを定めておくことが必要です。
㋥ 宗教団体では、「信者の情報」は、「絶対秘密」であり、「秘密厳守」です。
㋭ 信者個人の「信教の情報」は、①「信教の自由」「信教の秘密」を保護する観点から、絶対秘密であり、②家族・親族・友人・知人・恋人などからであっても、非開示を貫くべきですし、③弁護士・司法書士、銀行・郵便局・信用調査機関などにも、非開示であり、④病院・診療所、医師・看護師、社会福祉施設(老人ホーム)にも、非開示であり、⑤市区役所・町村役場、保健所、税務署、年金機構、生命保険会社にも、非開示ですが、⑥裁判所・検察庁・警察・外務省などからの問合せにも、非開示とすべきですし、⑦裁判所に証人喚問されたとしても、証言拒否をするのが妥当でしょう。⑧他の宗教団体からの照会にも、答えるべきではありません。
⑶ 「トランスペアレンシー(透明性)」
㋑ 社会的存在である諸団体には、①「トランスペアレンシー(透明性)」が求められていおり、②団体の運営や事業内容、人事異動・懲戒処分などを「閉鎖空間」で処理することは否まれ、③災害・事故や不祥事などに関する意思決定が、「密室に隠蔽」されないように求められます。
㋺ 「トランスペアレンシー(透明性)」とは、①「すべての意思決定は公開されなければならない」ことではありませんし、②すべてを公開すべきものでもありません。
㋩ 公開する必要があるのは、①意思決定の組織や手順があらかじめ定められていること、②その都度または定期的に報告がされていること、③秘匿しなければならないもの以外のものを公開していること、です。
㋥ 宗教団体では、①宗教の教義や信者に関することは「非開示」ですし、②宗教職の任免に関することなども「非開示」であり、③宗教的な判断に基づくものについては、「非開示」です。
⑷ 「CSR(社会的責任)」
㋑ 企業では、①単に求められて開示し、一定の事項を公開するだけではなく、不十分とされており、②積極的に社会に関与し貢献していくべきであるということからの責任が問われています。③それが、「CSR(コーポレート・ソーシャル・リスポンシビリティ、企業の社会的責任)」です。
㋺ 宗教団体にも同様のことが言えますが、①注意が必要であり、②企業と宗教団体の根本的な違いを失念すると大変です。
㋩ 企業・営利法人の場合、①当然、本来的に、「営利が目的」であり、②営利企業が、営利外の社会活動・社会貢献・公益事業などを行えば、賞賛されますし、③行政上の優遇措置があり、税務上の減税・免税などの恩典があります。
㋥ 宗教団体・宗教法人は、①元々、「宗教」という、公益活動を行う公益団体・公益法人ですから、②その上、宗教活動以外の公益事業・社会貢献などを行うことは期待されていません。③逆に、法律違反を咎められ、課税措置を受けることにもなります。
4 「アカウンタビリティ(説明責任)」
⑴ 三つの「責任」
㋑ 日本語の「責任」を説明する英語には、①「リスポンシビリティ(Responsibility)」、②「ライアビリティ(Liability)」、③「アカウンタビリティ(Acountability)」の、三つがあります。
㋺ 「リスポンシビリティ(Responsibility)」は、契約などに基づいて、相手方との関係で果たすべき「応答責任」を意味します。
㋩ 「ライアビリティ(Liability)」は、製造物責任など、物を信頼して使用している利用者の信頼に応える「信頼責任」を意味します。
㋥ 「アカウンタビリティ(Acountability)」は、社会的な負託を受けていることに対応して所要の説明をする「説明責任」です。
⑵ 「アカウンタビリティ(説明責任)」
㋑ 「アカウンタビリティ(説明責任)」は、①社会の中で活動している企業や法人に求められるものですが、②それは、社会的な負託を受け、社会的な協力を受けながら存在し、活動しているからであり、③その活動の内容などについて、社会的な説明をすることが求められています。
㋺ 宗教団体においては、①宗教活動のすべてについて説明責任が問われるわけではありませんが、②社会的な関心のある事項、世俗的な事項については、説明責任が求められており、③適切な時期に、適切な方法で、適切な説明をすることが必要です。
・
5 内部統制・組織管理
⑴ 内部統制の必要性
㋑ 「内部統制(Internal Control)」とは、組織が、組織として、適正に運営されるための制度・システムをいいます。
㋺ 組織が、設立の目的や本旨に従って、適正に、円滑に、効率的に運営されるためには、整えられた「組織管理(Organization Management)」が必要です。
㋩ 「内部監査」「内部監督」と言われることもあります。
㋥ もともと、営利企業である株式会社の論理なので、投資の有効性や営利目的の達成に要点が置かれていますが、宗教団体においては、別の観点からの必要性があります。
⑵ 内部統制の要点
① 組織の形成・運営に関する規範(ルール)を明確に定めること。
② 業務に関する情報の収集、情報の分析、情報の判断、意思の決定、決定の実行、実行の報告、報告の審査が、適正に行うこと。
③ 所与の物資・財産・人材を有効に活用し、無理や損傷を来さないこと。
④ 意思決定、指揮命令、結果判定、情報伝達、業務監査が適正に行われること。
⑶ 外部役員の有用性
① 株式会社の社外取締役・社外監査役、諸法人の外部理事・外部監事と同様に、宗教団体・宗教法人においても、外部役員(理事・議員・参事など)・外部責任役員を起用することが重要です。
② 外部役員を起用する前段階として、あるいは併用として、外部の有識者を顧問・相談役・参与などとして起用することも有益です。
③ 当事務所では、宗教団体・宗教法人のための、無償・低額の顧問受託や役員就任を行っています。
⑷ 宗教団体における内部統制
① 宗教の本旨から、右にも左にも逸れることなく運営されること。
② 教義教理の根本に損うことなく、弁解なく、適性・的確に運営されること。
③ 神仏に奉献された金銭・財産・物資・人材を損なうことなく運営されること。
④ 宗教職・職員・信者らが、人や政府などに忖度することなく、神仏に責任をはたすこと。
⑤ 神仏から委ねられた宗教団体を適正に運営すること(絶対的使命)。
・
6 内部通報・公益通報
⑴ 内部通報制度の構築
⑵ 法律による公益通報制度
7 本人確認
⑴
・

(グアムのホテルにて)
Ⅱ リスクマネジメント(RM)
1 リスクとマネジメント
⑴
2 RMのルール
⑴
3 危機管理
⑴
4 不祥事対策
⑴ 不祥事があった場合
⑵ 不祥事の調査
⑶ 不祥事の公表
5 クレーマー対策
⑴ 専用窓口の設置
㋑ 宗教団体は、企業や行政機関と同様、宗教団体も社会の中に存立する「社会内組織」です。
㋺ 社会内組織には、社会に向かって説明する責任「アカウンタビリティ」があります。
㋩ 「クレーマー」には、①真に権利の侵害や損失を被って、その対応を求める被害者もいれば、②単に自己の主義主張と異なるという理由で異議を述べる者もいれば、③金銭目的で事実を曲げて抗議に及ぶような悪質な者もいます。
㋥ これらのクレーマーに適切に対応するには、「専用窓口」を設置しておくことが必要です。
⑵ 専用窓口がないと……
㋑ 万事の処理・対応では、最初・端緒が最も肝心です。
㋺ 専用窓口がないと、端緒・入口で躓いてしまい、取り返しのつかない状態に堕ってしまうことが多々あります。
㋩ 専用窓口では、クレームの種類・内容・状況・日時・場所などを正確に聞き取ります。これが確定できていないと、後日、事案が大きくなったり、別の問題にすり替わったり、複雑な状況を生み出してしまいます。
㋥ 専用窓口では、クレーマーの住所・氏名・年齢・所属・立場・職業・家族など、クレームの対応に必要な人物に関する事項を特定します。これができていないと、後日、①人物が入れ替わったり、②自分は代理人だと主張して、別の本人が合わられたり、③合意した後に、あれは無権代理人だから無効だと言われたりしかねません。
㋭ 専用窓口がないと、最初に対応した人が、①狼狽てしまい、②安易な約束をしてしまい、③怒りを惹起・増長させてしまうなどの失敗を犯してしまいやすい。
㋬ 専用窓口がないと、対応がうまくいかずに、①悲鳴や泣き声を上げられ、②苦痛を訴えられ、③転倒され、④大声や粗暴な行為をされるなどがありえます。
㋣ 専用窓口がないと、対応がうまくいかずに、①事務所内を歩き回られ、②勝手に責任者の部屋に入り、③仲間を呼ぶなど、事態が深刻になってしまいます。
㋠ 専用窓口がないと、対応がうまくいかずに、責任者・代表者が対応を迫られ、即座の安易な約束を迫られたりします。
⑶ 専用窓口の周知
㋑ 専用窓口を定めたら、HP・パンフレット・チラシ・看板などで公表・周知します。
㋺ 専用窓口を定めたら、担当者以外の者がその業務を代行することはしない。
㋩ 専用窓口については、受付時間、休日対応、夜間対応などを明確に定めて、周知します。
⑷ 答えるべき内容
㋑ 専用窓口では、「答えるべき内容」を予めはっきりと決めておきます。
⑸ 答えるべきでない内容
㋑ 専用窓口では、①信教の自由に抵触する内容、②個人情報に関する内容、③信教の秘密・プライバシーに関する内容などは答えるべきではありません。
㋺ 専用窓口では、即座の約束はするべきではありません。
⑹ 録音・録画の周知
㋑ 専用窓口では、「すべて録音・録画」を原則とし、周知しておきます。
㋺ 電話の場合は、最初に「すべて録音」の旨を伝える。
㋩ 録音・録画の旨を伝えることによって、無謀な主張などを防ぐ効果があります。
6 「多数リスク」「少数リスク」
⑴ 民主政治の多数政治
㋑ 民主政治の基本は「多数政治」です。
㋺ 数人・数十人規模の団体であれば、「全員一致」の「合意政治」も可能です。
㋩ しかし、百人規模となると、「全員一致」の合意を得ることは困難です。
㋥ 千人・万人の規模、数億人の国家レベルでは、「全員の合意」は不可能です。
㋭ 自ずと「90%の圧倒的多数決」「¾以上の特別多数決」「過半数の多数決」などによらざるを得ません。
㋬ 場合によっては、「30%の多数意見」「1割の最多数決」もあります。
⑵ 「多数リスク」
㋑ 危機管理も、基本的に、「多数政治」によらざるをえません。
㋺ しかし、そこには、新たなリスクが発生します。
㋩ 危機管理がリスクを発生するという矛盾構造です。「多数リスク」です。
㋥ 「危機管理」は「多数決」に馴染むものではありません。
㋭ 「危機管理」は、人間の希望的観測や願望によってできるものではありません。
㋬ 「危機管理」は科学的知見に基づきますが、その根本は永遠の宗教的根源です。
⑶ 「少数リスク」
㋑ 比較的小さな集団で、「全員の完全合意」で進められる危機管理なら問題ありませんが、完全合意でなければ、必ず「反対者」「異見者」「不同意者」がいます。
㋺ 「危機管理」で問題となるのは、これら少数者の小さな行為です。
㋩ 堅固に構築された堤塁も「蟻の一穴」で崩壊に瀕するとの喩えもあります。
㋥ 米映画「コンテイジョン」「アウトブレイク」「第七の封印」「インヴェージョン」などや日本映画「感染列島」なども。
㋭ 「自由の誤解」から、世界に危機を分散・拡大し、大きな危機を招いてしまうことが予想されます。
㋬ 逆に、自由を弾圧・制限し、少数者を強圧し、「恐怖政治」の危機に至ることも。
・

(中国・万里の長城)
Ⅲ 犯罪被害者の支援
1 公判手続の傍聴
㋑ 犯罪被害者は、「加害者の刑事裁判の傍聴」ができます。
㋺ 裁判長への手続きが必要です。
2 公判記録の閲覧・謄写
⑴ 加害者の刑事事件
㋑犯罪被害者は、係属裁判所に申出て、㋺「加害者の刑事裁判の公判記録」を閲覧し、㋩「加害者の刑事裁判の公判記録」を謄写(コピー)することができます。
⑵ 加害者の他の刑事事件
㋑犯罪被害者は、係属裁判所に申出て、㋺加害者や共犯者による、㋩同様の態様で継続的・反復的に行われた同一・同様の犯罪の刑事裁判の、㋥公判記録を閲覧・謄写(コピー)することができます。
3 犯罪被害者の証人尋問
⑴ 犯罪被害者が証人となる場合
㋑加害者(被告人)の前では、著しく不安・緊張を覚えるおそれがある場合には、㋺不安・緊張を緩和するのに適当な者(付添人)を付き添わせることができます。
⑵ 犯罪被害者が証人となる場合
㋑加害者(被告人)の前では、圧迫を受け精神の平穏を害するおそれがある場合には、㋺被告人と証人との間に、㋩相手の状態を認識することができない遮蔽措置(パーテーション)をすることができます。
⑶ 犯罪被害者が証人となる場合
㋑加害者(被告人)のいる法廷では証言するのが困難なときは、㋺裁判所の構内の別室にて、㋩映像と音声の送受信によって(ビデオリンク方式)尋問することができます。
4 被害者参加
⑴ 犯罪被害者は、
申し出て、裁判所の許可を得て、加害者の刑事裁判に参加することができます。「被害者参加人」となります。
⑵ 被害者参加人には、
公判期日が通知され、公判期日に出席することができます。
⑶ 被害者参加人は、
検察官に意見を述べることができます。
⑷ 被害者参加人は、
犯罪事実に関する情状事実について、証人を尋問することができます。
⑸ 被害者参加人は、
被告人に供述を求める質問をすることができます。
⑹ 被害者参加人は、
事実と法律の適用に関する意見を陳述することができます。
⑺ 被害者参加人が、
著しく不安・緊張を覚えるおそれがあるときは、不安・緊張を緩和するのに適切な者(付添人)を付き添わせることができます。
⑻ 被害者参加人が、
圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあるときは、被告人から被害者参加人の状態が認識されないように、遮蔽措置(パーテーション)を採ることができます。
⑼ 被害者参加人に対しては、
旅費、日当、宿泊料が支給されます。
5 刑事裁判における民事上の和解
⑴ 刑事裁判の過程で、
被告人と被害者が、民事上の争いについて合意したときは、刑事裁判の過程で「和解調書」が作成され、民事上、強制力のある和解となります。
⑵ 別に、民事裁判を起こすなどしなくてすみます。
6 刑事裁判における損害賠償請求
⑴ 犯罪被害者は、
係属刑事裁判所に、「損害賠償命令」の申立てをすることができます。
⑵ 「損害賠償命令」が発せられると、
民事訴訟手続をする必要がなくなります。
・


(カンボジア・シュムリアップにて)
Ⅳ ストーカー対策
1 「ストーカー行為」とは
・ 「同一の者」に対して「つきまとい等」を反復してすることを言います。
2 「つきまとい等」とは
・ 「つきまとい等」とは、
・ ㋑ 特定の者に対する恋愛感情、好意の感情、不満の怨念の感情を充足する目的で、
・ ㋺ 特定の者・配偶者・直系親族・同居親族など、密接な関係のある者に対して、
・ ㋩ 次の「つきまとい等の行為」を行うこと、をいいます。
3 「つきまとい等の行為」とは
・ ① つきまとい、待ち伏せ、進路の立ち塞ぎ、
住居などへの押し掛け、住居などの付近での見張り、住居などの付近でのみだりなうろつき
・ ② 行動の監視を暗示すること
・ ③ 面会や交際などの要求
・ ④ 著しく粗野・乱暴な言動
・ ⑤ 無言電話
・ ⑥ 拒まれたのに、連続して、電話、ファックス、電子メールすること
・ ⑦ 汚物、動物の死体、不快嫌悪な物を送り付けること
・ ⑧ 名誉を害することを告げること
・ ⑨ 性的羞恥心を害することを告げること
・ ⑩ 性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録媒体を送り付けること
・ ⑪ 性的羞恥心を害する電磁的記録の送信
4 つきまとい等の禁止
・ 誰でも、つきまとい等をして、
・ 身体の安全、住居の平穏、名誉が害されるという不安を覚えさせ、
・ 行動の自由が著しく害されるという不安を覚えさせてはなりません。
5 警察署長の警告
・ つきまとい等をされた者から、警察署長に申し出て、
・ 更に、反復して行うおそれがあると認めるときは、
・ 警察署長から、行為者に対して、
・ 更に反復して行ってはならない旨の「警告」が発せられます。
6 公安委員会の禁止命令
・ ㋑ 公安委員会は、更に反復して行うおそれがあると認めるときは、
・ ㋺ つきまとい等をされた者からの申し出によりまたは職権で、
・ ㋩ 行為者に対して、
・ ① 更に反復して行ってはならない旨、
・ ② 更に反復して行うことを防止するために必要な事項を命令します。
7 ストーカー対象者の情報提供の禁止
・ ストーカーをするおそれがある者に、
・ ストーカー行為の相手方の氏名・住所などの情報を提供してはなりません。
・

(中国江蘇省・揚州「大明寺」)
Ⅴ 暴力団の排除
1 根拠法令
① 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」
② 「東京都暴力団排除条例」(各地方公共団体も同様)
2 定義
⑴ 暴力団等
① 「暴力団」
・ 構成員が集団的・常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体。
② 「指定暴力団」
・ 構成員が集団的・常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれが大きい暴力団。
③ 「指定暴力団連合」
・ 指定暴力団の連合体。
④ 「指定暴力団等」
・ 指定暴力団、または、指定暴力団連合。
⑤ 「上方連結」
・ 指定暴力団等型の指定暴力団等の構成団体となる関係、
・ または、指定暴力団等の代表者等が他の指定暴力団等の暴力団員となっている関係。
⑥ 「系列上位指定暴力団等」
・ その指定暴力団等と上方連結することにより順次関連している各指定暴力団等。
⑦ 「暴力団事務所」
・ 暴力団の活動の拠点となっている施設・施設の区画された部分。
⑧ 「暴力団員」
・ 暴力団の構成員。
⑨ 「指定暴力団員」
・ 指定暴力団等の暴力団員。
⑩ 「暴力団関係者」
・ 暴力団員、暴力団・暴力団員と密接な関係がある者。
⑵ 暴力的不法行為等
1 爆発物取締罰則の罪
2 刑法の罪
3 暴力行為等処罰に関する法律の罪
4 盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪
5 労働基準法の罪
6 職業安定法の罪
7 児童福祉法の罪
8 金融商品取引法の罪
9 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の罪
10 大麻取締法の罪
11 船員職業安定法の罪
12 競馬法の罪
13 自転車競技法の罪
14 建設業法の罪
15 弁護士法の罪
16 火薬類取締法の罪
17 小型自動車競走法の罪
19 毒物及び劇物取締法の罪
20 港湾運送事業法の罪
21 投資信託及び投資法人に関する法律の罪
22 モーターボート競走法の罪
23 覚醒剤取締法の罪
24 旅券法の罪
25 出入国管理及び難民認定法の罪
26 宅地建物取引業法の罪
27 酒税法の罪
28 麻薬及び向精神薬取締法の罪
29 武器等製造法の罪
30 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の罪
31 売春防止法の罪
32 銃砲刀剣類所持等取締法の罪
33 割賦販売法の罪
34 著作権法の罪
35 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の罪
36 火炎びんの使用等の処罰に関する法律の罪
37 建設労働者の雇用の改善等に関する法律の罪
38 銀行法の罪
39 貸金業法の罪
40 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の罪
41 港湾労働法の罪
42 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律の罪
43 不動産特定共同事業法の罪
44 保険業法の罪
45 資産の流動化に関する法律の罪
46 債権管理回収業に関する特別措置法の罪
47 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律の罪
48 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の罪
49 自転車競技法の罪
50 小型自動車競走法の罪
51 モーターボート競走法の罪
52 覚醒剤取締法第の罪
53 旅券法の罪
54 出入国管理及び難民認定法の罪
55 麻薬及び向精神薬取締法の罪
56 武器等製造法の罪
57 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の罪
58 売春防止法の罪
59 銃砲刀剣類所持等取締法の罪
60 著作権法第の罪
61 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の罪
62 火炎びんの使用等の処罰に関する法律の罪
63 貸金業法の罪
64 麻薬特例法の罪
65 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律の罪
66 組織的犯罪処罰法の罪
67 会社法の罪
68 組織的犯罪処罰法の罪
69 著作権等管理事業法の罪
70 高齢者の居住の安定確保に関する法律の罪
71 使用済自動車の再資源化等に関する法律の罪
72 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の罪
73 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の罪
74 信託業法の罪
75 探偵業の業務の適正化に関する法律の罪
76 犯罪による収益の移転防止に関する法律の罪
77 電子記録債権法の罪
78 資金決済に関する法律の罪
⑶ 暴力的要求行為
3 禁止行為
⑴ 暴力的要求行為の禁止
① 指定暴力団員は、所属する指定暴力団や系列上位指定暴力団等の威力を示して暴力的要求行為をしてはなりません。
② 何人も、指定暴力団員に対して、暴力的要求行為を要求・依頼・教唆してはなりません。
③ 何人も、指定暴力団員の暴力的要求行為の現場に立ち合い、暴力的要求行為を助けてはなりません。
⑵ 対立抗争時の事務所の使用制限等
⑶ 加入の強要等の規制等
4 暴力団排除活動
⑴ 暴力団排除活動の基本理念
㋑ 暴力団が都民の生活や都の区域内の事業活動に不当な影響を与える存在であるとの認識の下、
㋺ ①暴力団と交際しないこと、②暴力団を恐れないこと、③暴力団に資金を提供しないこと、④暴力団を利用しないことを基本として、
㋩ 都・特別区・市町村・都民・事業者の連携・協力により推進する。
⑵ 禁止行為
① 妨害行為の禁止
何人も、次の行為を妨害してはなりません。
㋑ 暴力団からの離脱援助の雇用機会提供・就労斡旋・住居提供・資金提供
㋺ 暴力団員の利用を制限している不特定・多数者の供用施設の、暴力団員の利用拒絶
㋩ 青少年の暴力団加入や暴力団員による犯罪被害の防止指導・助言など
㋥ 祭礼等行事について、暴力団・暴力団員の運営関与・行事参加の拒絶
㋭ 事業者の事業契約の特約による契約解除など
㋬ 不動産譲渡者等の当該契約の特約による契約解除・買戻
㋣ 不動産の譲渡等の代理・媒介者の、暴力団事務所供用の知情後、代理・媒介の拒絶
㋠ 利益供与の拒絶
㋷ 自己の名義利用の拒絶
② 暴力団事務所の禁止
次の施設の敷地の周囲200mの区域内では、暴力団事務所を開設し、運営することはできません。
㋑ 学校(大学を除く)、高等専修学校
㋺ 家庭裁判所
㋥ 児童福祉施設・児童相談所・類似施設
㋭ 少年院
㋬ 少年鑑別所
㋣ 公民館
㋠ 図書館
㋷ 博物館
㋦ 保護観察所
㋸ 主として外国人青少年対象の各種学校
㋾ 博物館相当施設
㋻ 青少年教育施設
③ 利益供与の禁止
事業者は、その事業について、次の行為の対償として、利益供与してはなりません。
㋑ 暴力的不法行為等
㋺ 暴力的要求行為
㋩ 暴力的要求行為の現場に立ち合い・助ける行為
④ 名義利用の禁止
暴力団員は、暴力団員を隠蔽するために、他人の名義を利用してはなりません。
何人も、情を知って、暴力団員に、自己の名義を利用させてはなりません。
・
・

Ⅵ 幼児虐待・児童虐待への対応
1 幼児虐待・児童虐待の発見
㋑ 神社・寺院・教会などには、幼児や児童が多く通っています。
㋺ 宮司・禰宜・住職・牧師・司祭・教師などの宗教職は、幼児・児童の平常を知っています。
㋩ そのため、幼児虐待・児童虐待などを発見しやすい立場にいます。
㋥ あらかじめ、対応策を検討しておくことが必要です。
2 虐待されている幼児・児童虐待への対応
3 虐待している親などへの対応
・

Ⅶ 秘密の保持
1 信仰の秘密・宗教の秘密
⑴ 「信仰の秘密」
㋑ 「信仰の秘密」は、宗教を信仰することに関する個人の自由権の一つです。
㋺ 個人がどんな宗教を信仰しているかを問われない権利です。
㋩ 個人が、外部から影響されずに、自己の意思で自由に、信仰心を表せる権利です。
㋥ 他人は、個人の宗教や信仰に関して、本人の意思に反して、問い詰めてはいけません。
㋭ 「宗教による差別」「信仰による差別」「宗教弾圧」などから、個人を守る権利です。
⑵ 「宗教の秘密」
㋑ 「宗教の秘密」は、個々の宗教の信仰者の全体、宗教団体、宗教職などの権利です。
㋺ 個々の宗教の教義、信仰、組織、運営などに関して、他から干渉されない権利です。
㋩ 宗教や信仰が、秘密結社であり、反社会的なことであるということではありません。
㋥ 宗教弾圧、宗教差別、宗教強制などから守られ、真理に従い、正義を行う権利です。
⑶
2 プライバシーの保護
⑴ 私事権
㋑ 「プライバシー」とは、「一人にしておいてもらう」個人の権利です。
㋺ 「他人に干渉されない」「他人から構われない」という、消極的な権利です。
㋩ 「社会から隠れて秘密裡に事を行う」という悪い意味ではありません。
㋥ 正しいこと、正当なことでも、個人的なことは、他人に見られ、知られたくない権利です。
⑵
⑶
3 個人情報の保護
⑴
・

(京劇「三国志」)
Ⅷ ハラスメントの防止
1 ハラスメントとは
⑴ 「ハラスメント」は、一定の人間関係の中で起こる問題です。
㋑ 具体的には、①労働者と使用者との労使関係、職場における上司と部下との関係、②職場や学校やスポーツなどの世界における先輩と後輩との関係、③取引先との関係、趣味や技芸の関係、恋愛関係、交友関係、④学校における先生と生徒との関係、地域社会における先住者と後住者との関係など、 一定の力関係がある場合に、
例えば、上下の関係、先後の関係、優先劣後の関係、依存・被依存の関係などがある「個人と個人の間」で起こる問題です。
㋺ したがって、無関係な個人と個人の間で起こることはありませんし、集団の中で起こる「いじめ」とは別の問題です。
⑵ 「ハラスメント」とは、相手方が「嫌がる」ことです。
㋑ 相手方を「嫌がらせる」ことではありません。
㋺ 行為者には相手方を「嫌がらせる」意図や意思がなくても「ハラスメント」に当たることがあります。
㋩ 「嫌がる」ことには、相手方が「不快に感じた」「プライドを傷つけられた」「嫌な思いをした」「脅威を感じた」「不利益を感じた」などあらゆることが含まれます。
⑶ 「ハラスメント」は、相手方に与える心理的な効果が問題とされます。
㋑ 行為者の「発した言葉」「した行為」「とった行動」「振る舞い」などが問題とされます。
㋺ それを相手方がどう受け止め、どう心理的に影響したかが問題とされます。
㋩ したがって、①行為者が実際に権限を有しているか否か、②その言葉や行為・行動などが実際に効果を生じるか否か、③法的に効力を有するか否かなどとは、直接には、関係がありません。
⑷ 「ハラスメント」は、多種多様です。
「セクシャル・ハラスメント(セクハラ)」「パワー・ハラスメント(パワハラ)」「モラル・ハラスメント(モラハラ)」「アカデミック・ハラスメント(アカハラ)」など、
2 セクシャル・ハラスメント(セクハラ)
⑴ 「セクハラ」とは、
㋑ 職場、学校、取引先、町内会、マンションなどにおいて、相手が不快に感じたり、嫌がったりする性的な言葉を発したり、性的な不快感などを与える行為、行動、仕草などをすることをいいます。
㋺ 男性から女性へという場合が比較的多いので男性から女性への問題と思われていますが、女性から男性へという場合、同性から同性へという場合も同様です。
⑵ 「セクハラの防止」は、
㋑ 男女雇用機会均等法(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律)では事業主の義務として規定されています。
㋺ 事業主は、職場での「性的な言動」への対応により労働者が労働条件上の不利益を受けたり、就業環境が害されないような措置を講じなければならず(11条)、女性労働者の妊娠・出産・産前産後休業などに関する言動により就業環境が害されないような措置を講じなければなりません(11条の2)。
㋩ 宗教団体や宗教施設でも、雇用関係のある職員の職場環境においては当然に適用されます。
⑶ 宗教団体や宗教施設における、
雇用関係にない宗教専門職(宮司・禰宜・住職・牧師・司祭・教会長・宣教師など)、宗教職(神官・僧侶・教職者・聖職者など)、修行者(宗教職となるための修行中の者)、信者(氏子・檀徒・信徒・教会員など)、信奉者・参詣者・参拝者など、宗教施設来所者などの間においても「セクハラ」は起こりうる問題です。
⑷ 宗教団体や宗教施設においては、
祈祷・祈願・相談・カウンセリング・信仰指導などの場で、宗教専門職・宗教職と信者・信奉者などという関係の中で「セクハラ」事案が起こりやすいので注意が必要であるのみならず、防止のための対策が必要です。
⑸ 宗教団体や宗教施設では、
宗教専門職・宗教職・修行者の間においてや、信者・信奉者などの間においても、上下関係や先輩後輩という関係が生まれ、その中で「セクハラ」事案が起こりやすいので、あらかじめ対策を講じておくことが必要です。
3 パワー・ハラスメント(パワハラ)
⑴ 「パワハラ」とは、
職務上の地位や、職業上の経験や技術の優劣、職場における人間関係などを背景に、その優位性をもとに、同じ職場で働く者に対して、業務上の適正妥当な範囲を超えて、叱責し、業務を命じ、行動や服装を規制し、同行や参加を求めるなど、相手方に精神的な負担を与え、身体的な苦痛を与え、職場環境を悪化させるような言動をいいます。
⑵ 「パワハラ」は、
職場だけではなく、同業者団体、経済経営団体、スポーツ団体、芸能団体、青少年団体などにおいても、その分野における地位や経験・実力・技術などの上下優劣に基づいて、同じ団体の構成員に対して、精神的な負担を与え、身体的な苦痛を与え、団体内部における活動を悪化させるような言動をいいます。
⑶ 宗教団体や宗教施設においても、
宗教専門職・宗教職・修行者の間において、信者・信奉者などの間において、宗教専門職・宗教職・修行者と信者・信奉者などとの間において、地位の上下、経験の長短、知識の深浅などという関係から「パワハラ」が起こる可能性があります。
4 宗教ハラスメント
⑴ 宗教団体や宗教施設において、
宗教専門職・宗教職・修行者の間において、宗教上の地位や、宗教上の覚悟・知識の深浅、宗教上の経験の長短などを背景に、上位・優位にある者が下位・劣位にある者に対して、宗教的向上心を削がれ、宗教的熱心を低下させ、宗教的敬虔を後退させ、宗教的信仰を減衰させ、延いては宗教職を断念させるに至るような言葉・行為・行動をすることを「宗教ハラスメント」と呼びます。
⑵ 同様のことは、
宗教専門職・宗教職・修行者から信者・信奉者などに対して行われる可能性もあります。信者・信奉者などの間においても起こりうることです。
⑶ 「宗教ハラスメント」は、
宗教団体や宗教施設における秩序を乱し、その正当な運営を困難にし、宗教団体そのものに対する信頼を欠くことになり、宗教活動の実行を困難にし、宗教団体の存続を危うくしかねません。宗教団体においては「宗教ハラスメント」を深刻に受け止め、未然防止のために、宗教職や信者などに対する教育や研修をしっかり行うなどのことが求められます。
5 ハラスメントの防止
⑴ 「ハラスメント」は、
特別の意図や意思があり、深い意味があって行うものではありませんから、受け手である被害者には深刻であっても、行為者にはその自覚が全くないということが少なくありません。むしろ、行為者には、職務や責任に忠実であり、相手方にとって利となることと思ってしたという認識である場合が多々です。
⑵ 「ハラスメント」は、
個人間の問題であり、受け手の特殊な事情に基づく場合が多く、受け手の受け方の問題でこともありますから、周囲の同僚や関係者にも気づかれることなく、被害者が「自分の問題」「自分の責任」と考え、一人で悩むことが少なくありません。
⑶ そのため、
「ハラスメント」に対しては、組織として十分な対応をとらないと深刻な事態を招いてしまいかねません。宗教団体としては、宗教団体の基範でその対応策の基本を規定し、宗教職などの倫理規程を定め、職員の就業規則に防止規定を置き、信者などのハンドブックにハラスメントの項目を置くなどのほか、宗教職や信者などに対する教育や研修を徹底する必要があります。
6 「逆ハラスメント」
⑴ 不正・不当・不合理なハラスメント被害主張
㋑ ハラスメント被害の主張のすべてが、正しく、正当であり、合理的なわけではありません。
㋺ 「ハラスメント」の名の下に、不正・不当な要求をするものもあります。
㋩ 単に自分の気に合わない者や行為を「ハラスメント」と言う場合もあります。
㋥ 一生懸命、誠心誠意で相手のために務めていても、「ハラスメント」と呼ばれることもあります。
⑵ 「逆ハラスメント」
㋑ ハラスメントは、上位・強者から下位・弱者へと、一定の力関係の中で起こる行為ですが……。
㋺ 全く正反対に、下位・弱者から上位・強者に向けても、ハラスメントが起こり得ます 。
㋩ ⑴のようなケースでは、加害者・被害者が逆転しています。
⑶ 依頼者との関係
㋑ 依頼者から、「依頼しなければならないという弱みがある」と主張されることがあります。
㋺ 受託者には、「依頼に応じる義務」があり、依頼者に対して「弱み」があります。
㋩ 本来、委任・委託・請負など、対等の立場での「契約」関係を認識する必要があります。
㋥ 委託者・受託者間での意識に差異が生じた場合、説明不可能なことが多いでしょう。
㋭ 「弱みにつけ込む」との疑念の回避には、関係を持たない以外に方法がありません。
㋬ 適切な説明をしようとしては、それ自体を「ハラスメント」と主張されないからです。
・
Ⅷ-2 信徒からのハラスメント
1 最近の相談事例
㋑ 「信徒から聖職者(牧師、住職、宮司など)に対するハラスメント」
㋺ 「一般に、
聖職者から信徒に対するハラスメントが問題とされているが、
信徒から聖職者に対するハラスメントはないのか?」
2 聖職者と信徒の関係
㋑ ハラスメントとは、
個人と個人との間に一定の関係がある場合に生じるものです。
㋺ 一般に、
上下、優劣、先後、強弱などの
地位、身分、職務、力関係などがある場合に起こりえます。
㋩ 通例、
聖職者と信徒との関係は上下に類する関係とみなされます。
㋥ そのため、
聖職者から信徒に対するハラスメントが問題にされます。
3 聖職者を労働者とする教会
⑴ 日本の小さな宗教団体では
㋑ 日本の小さな宗教団体の中には、
「聖職者は信徒が養っている」
という考えを持つ信徒(総代、役員)がいます。
㋺ そのような教会では、
聖職者と信徒の関係が逆転し、
信徒による聖職者に対するハラスメントが問題となります。
⑵ 聖職者を雇っている教会
㋑ そこでの「聖職者と信徒」の関係は、
「信徒が集まる宗教団体(宗教法人)が、聖職者を雇用している」
という雇用関係・労使関係にあります。
㋺ その場合、
一般の社会における「職場のパワーハラスメント」と全く同じで、
使用者である信徒(総代、役員)が労働者である聖職者に対して、
ハラスメントを働いているということになります。
㋩ そもそも、
聖職者が信徒に使用されている労働者では、
聖職者は信徒の指揮監督下に置かれ、
信徒の指揮に従って労働に服することになりますから、
神仏の働きはできません。
⑶ 源泉徴収問題
㋑ 聖職者を労働者とみなす扱いは、
第一に、税務署の指導にありました。
㋺ 聖職者からの所得税の徴収の方法として、
聖職者を労働者とみなして
その給与から源泉徴収することです。
㋩ 本来、
聖職者は労働者ではありませんから、
給料(給与)ではなく、謝儀(報酬)であり、
確定申告によるべきです。
⑷ 厚生年金問題
㋑ 聖職者を労働者とみなす扱いは、
第二に、年金事務所の指導にあります。
指導の域を超えた、強行な徴収に転じています。
㋺ その理由は、
年金機構が国税庁から入手したデータにあります。
㋩ 所得税の源泉徴収するのは、
労働者に対して給与の支払いをしている法人ということです。
㋥ 給与の支払いをしているのですから、
「労働者である」というの事実です。
㋭ 労働者を1人でも使用している法人であれば、
厚生年金への加入は義務(強制)です。
㋬ 宗教団体の中には、
「厚生年金に加入したい」と願って、
自ら労働者と偽る者もあります。
⑸ 労働社会保険関係
㋑ 聖職者が労働者であれば、
厚生年金だけに加入して終わりではありません。
㋺ 労働者を使用する法人は、
① 雇用保険
② 労働者災害補償保険(労災保険)
③ 健康保険
④ 厚生年金
に加入しなければなりません(強制加入)。
㋩ 聖職者が労働者でなければ、
① 国民健康保険
② 国民年金
に加入しなければなりません(強制加入)。
㋥ また、
労働者なのですから、当然に、
労働基準法
最低賃金法
労働契約法
労働組合法
男女雇用機会均等法
育児休業・介護休業等法
女性活躍推進法
労働安全衛生法
職業安定法
労働者派遣法
その他多数
の労働関係法令の適用を受けることになります。
⑹ ハラスメントの原因
㋑ 「信徒から聖職者へのハラスメント」の原因には、
根本的な意識の誤りもあるように思われます。
㋺ 法律関係、納税関係、社会保険関係などを正常な形に戻すことが
聖職者と信徒の関係を正常に戻すことになるのではないと思われます。

(中国四川省「樂山大仏」)
Ⅸ 「宗教詐欺」の被害防止
1 宗教団体などを狙った詐欺
⑴ 宗教団体を狙った詐欺
⑵ 宗教専門職を狙った詐欺
⑶ 宗教団体の中での信者などを狙った詐欺
⑷
2 宗教詐欺にあわないために
⑴
3 宗教詐欺にあったら
⑴

(マカオ・聖アントニオ教会)
Ⅹ クリーンハンドの原則
1 「盗人猛々しい(ぬすっとたけだけしい)」
⑴ 誤ってしまったた人の感覚
・ ㋑ 人には、意図せず、行為や判断を誤ってしまうことがあります。
・ ㋺ 失念、不注意、過失、事故、マナー違反、ルール違反、手続懈怠など。
・ ㋩ 非行、契約違反、不倫、不正行為、不当行為、法令違反、犯罪など。
・ ㋥ 「失敗した」「まずかった」「申し訳ない」「ごめんなさい」というのが通常の感覚でしょう。
・ ㋭ 人の本性・罪性として、「隠したい」「逃れたい」「免れたい」という思いはありましょう。
・ ㋬ しかし、現実に発覚し、咎められれば、謝罪し、賠償し、処分を受け、身を改め、行動を改めるのが、通常の人の感覚でしょう。
⑵ 誤った人権感覚
・ ㋑ 意図して悪事にふける人、人を騙して平然としている人、人から利益を奪って生活している人、人に被害を負わせてなんとも思わない人など、正常な感覚を失した人がいます。
・ ㋺ 「盗人猛々しい(ぬすっとたけだけしい)」という言葉があります。
・ ㋩ 文字通りには、他人の物を盗んでおきながら、逆に、自分を責め・咎める者に喰ってかかる人です。
・ ㋥ 悪事を働いて咎められると居直り、逆に、激昂するような人のことです。
・ ㋭ さらに、平然と悪事を働き、悪事を働きながら正義の人・良い人を装う人です。
・ ㋬ 小説やドラマの世界だけではなく、実際に、政界・経済界・宗教界にも、そういう人がいます。
2 「クリーンハンドの原則」
⑴ 権利を主張する者は
・ ㋑ 英米法に「クリーンハンドの原則」という法理があります。
・ ㋺ 「He who comes to the court of equity must come with clean hands.」というものです。
・ ㋩ 直訳すれば、「裁判所に来る者は聖い手をもって来なければならない」というものです。
・ ㋥ 「権利を主張し、訴えを起こすなら、自分に非があってはならない」ということです。
⑵ 自己の非を棚に上げて
・ ㋑ 日本には「棚に上げる」「自分のことは棚に上げる」という諺があります。
・ ㋺ 「自分の非は放置して、相手を責める」「自分のことは知らん顔をする」「自分にとって不都合なことは無視する」という意味です。
3 「神」という意識
⑴ 無神論者・無宗教者・唯物論者の世界
・ ㋑ 日本では、戦後、徹底した「無宗教教育」「唯物論教育」が行われてきました。
・ ㋺ 結果的に、徹底した「無神論・無宗教・唯物論の国」となっています。
・ ㋩ 目に見える物・手で触れる物・形ある物だけの世界です。
・ ㋥ 当然、「神」は否定され、「神」という意識はありません。
⑵ 唯物論の価値観
・ ㋑ 唯物論の世界では、「人に見られていなければ、何をしても良い」という感覚に陥りやすくなります。
・ ㋺ 悪事や非行が咎められると、「証拠は?」「証拠を出せ!」と主張します。
・ ㋩ 逆に、被害者が咎められ、加害者が居直る現象ともなっています。
⑶ 「神の目」「神の裁き」という意識
・ ㋑ 無宗教者にかけているのは、世界の統治者である「神」という意識です
・ ㋺ 人の目の届かないところにも、「神の目」あるという意識です。
・ ㋩ 正義の神・公平公正の神であれば、必ず「神の裁き」があるという意識です。
・ ㋥ 神の前には、絶対に、クリーンハンドでなければ立ち得ません。
・

(出羽三山・月山神社の龍)
Ⅺ リスクと経営
1 リスク経営
⑴
⑵
⑶
2 リスク回避
⑴
⑵
3 リスク回復
⑴
⑵
・

(グアムのカトリック教会)
Ⅻ リスクと事業継続計画(BCP)
1 自然災害の増加・巨大化と災害リスク対応
⑴
⑵
⑶
2 高齢化・後継者問題と経営リスク対応
⑴
⑵
3 事業継続力強化計画(事業強靭化)
⑴
⑵
・

東京都(小池知事=右)と東京都宗教連盟(小野理事長=左)との防災協定締結
(櫻井参与=中)・・・・・・新聞記事より
XⅢ 防災・災害対策・被災者支援
1 防災と災対
⑴ 「防災」とは、あらかじめ災害の防止を目指して行う諸活動をいいます。
⑵ 「災対」とは、災害の発生後に、直ちに行う諸活動をいいます。
⑶ 平常時にあらかじめ災害に備えて行う「防災」は大切ですが、㋑ 災害の発生後は、発生した災害に即応し、㋺ 危機にさらされている生命・身体・財産のための「災対」には緊急性があります。
⑷ 具体的に発生した災害のための「災対」には、広範囲・中範囲・小範囲・局所の各団体で、即座に対応しうる指導者(災対コーディーネーター)の働きが重要です。
⑸ 「災対」は、「防災」を基礎とし、「防災」として備えられた用具用品・備蓄食水・備蓄生活具・機器・車両などを使用し、組織・人材を活用して行います。
2 防災
⑴ 防災の第一は、㋑発生するおそれのある災害に対して、被害を生じさせない対策です。㋺境内地・境内建物・施設・装備・備品の耐震化・暴風雨対策・水害対策・非常電源設備・非常食水対応などがあります。
⑵ 防災の第二は、㋑発生した災害に対して、主として「生命の安全」を守護する対策です。㋺これには、避難場所、食料、飲料、衣服、寝具などの備蓄ほか、情報の収集と発信のための設備も必要です。
⑶ 防災の第三は、㋑災害が発生した場合に、主として「生命の危険」を回避する対策です。㋺この一つは、むやみな帰宅や避難を促進せず、現在の場所において耐えることです。㋩宗教団体や施設における「一斉帰宅の抑制」「耐久避難の対応」も重要です。
3 災対
⑴ 災害対策の第一は、「自己の安全」を確保することです。
⑵ その第一は、㋑関係者の「生存と安全」です。㋺関係者の生命を危険に晒しては本末転倒です。㋩それには、衣食眠の基本を充足しうる物品の備蓄が必要です。
⑶ その第二は、㋑「情報の収集と発信」です。㋺そのためには、非常時に対応可能な「衛星携帯電話」の設置と、㋩情報機器(ラジオ・テレビ・コンピュータ)に専用の「発電機」「蓄電池」の設置が不可欠です。
⑷ その第三は、㋑「緊急即応の指揮体制」です。㋺全体を俯瞰した権限と責任ある「総括指揮者(総括災対コーディネータ)」と、㋩局所的な現場で総合的な指揮を行う「現場指揮者(各部災対コーディネータ)」を、㋥平時から任命し、配置しておくことが必要です。
⑸ 「災対本部」には、㋑過去の経験やこの先の不安に惑わされず、㋺現時点における、迅速かつ責任ある対応が求められます。
4 電子情報の防災
⑴ 現代の宗教団体・宗教法人の諸情報は、ほぼ例外なく、電子機器の電子情報として保存されています。
⑵ 電子情報は電気に依存しますから、㋑停電や電池の消耗の結果、電子機器が使用できなくなると、㋺電子情報を開くことができなくなります。㋩最悪の場合、電子情報に欠損を生じたり、消失してしまうこともあります。
⑶ そのため、防災として、常時、電子機器に専用の電源(発電機、蓄電池)を確保することが必要になります。
5 被災者支援
⑴ 現代の宗教団体・宗教法人の諸情報は、ほぼ例外なく、電子機器の電子情報として保存されています。
・

(韓国ソウル市内、監視カメラ)
XⅣ 防犯カメラ・監視カメラ
1 防犯カメラ・監視カメラとは
「防犯カメラ・監視カメラ(以下「防犯カメラ」)」とは、㋑犯罪行為・違法行為・迷惑行為・粗暴行為・禁止行為などの予防や防止を目的に、㋺境内地・境内建物に設置し、㋩不特定多数の人やその行為・風態などを継続的に撮影し、㋥メモリー(画像記録装置)を有するものをいいます。
2 防犯カメラの設置
防犯カメラの設置・運用・利用などに関しては、地方自治体(都道府県、市区町村)によって、条例・施行規則・ガイドラインなどが定められています。
・
・
 岩陰から恐竜が・・・ (カリフォルニア「ユニバーサルスタジオ」)
岩陰から恐竜が・・・ (カリフォルニア「ユニバーサルスタジオ」)
XⅤ 感染症の防疫対策
1 感染症とは
(「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」)
⑴ 一類感染症
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘瘡、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱。
⑵ 二類感染症
急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、重症性呼吸器症候群(サーズ)、中東呼吸器症候群(マーズ)、特定鳥インフルエンザ。
⑶ 三類感染症
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス。
⑷ 四類感染症
㋑E型肝炎、A型肝炎、黄熱、Q熱、狂犬病、炭疽、鳥インフルエンザ、ボツリヌス症、マラリア、野兎病、㋺その他政令で定めるもの。
⑸ 五類感染症
㋑インフルエンザ、ウイルス性肝炎、クリプトスポリジウム症、好転生免疫不全症候群、性器クラミジア感染症、梅毒、麻疹、メリシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、㋺その他省令で定めるもの。
⑹ 新型インフルエンザ等感染症
新型インフルエンザ、再興型インフルエンザ。
⑺ 指定感染症
㋑法定の措置を取らないと、㋺当該疾病の蔓延により、㋩国民の生命・健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの。
⑻ 新感染症:
㋑人から人へ伝染すると認められる疾病であって、㋺既知の感染症とは病状や治療の結果が明らかに異なるもので、㋩当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、㋥当該疾病の蔓延により国民の生命・健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの。
・
2 防疫対策
⑴ 宗教団体の防疫体制
① 宗教団体は医療機関ではないのですから、「完全な防疫体制」を構築するのは不可能か著しく困難です。
② 宗教団体で構築する「防疫体制」とは、非常の場合に構築する「緊急の防疫体制」のことです。
③ 「緊急の防疫体制」は、非常事態に陥ってから構築できるものではありませんから、予め「非常時における緊急の防疫体制」を想定しておくことが必要です。
④ それを実効的にするために、「緊急防疫体制マニュアル」を定めておくことが必要です。
⑵ 宗教施設の防疫設備
① 宗教団体において期待される防疫設備としては、あくまでも初期対応の設備です。高度な専門的な設備が求められるものではありません。
② 平時から感染症予防の意味で、手洗い、アルコール消毒、マスクの常備、トイレの清掃などを励行することです。
③ 「感染症発生のおそれ」がある場合には、該当者を個室に隔離し、多数の人との接触を回避し、感染症の拡大を防止することです。
④ 宗教団体においては、「慈悲の精神」「愛の精神」などがあり、自己犠牲的な行動をとる可能性などもありますから、そのことを事前に想定し、十分な対応策を実施することが必要です。
⑤ 次いで、感染症の防疫対策で肝心なことは、「汚染されていないエリア」(安全なエリア)を確実に確保することです。
⑥ このエリアは、完全に分離し、入室者を明確に限定し、部屋の出入りを厳重に管理することが必要です。
⑶ 信者・来参者・職員などの防疫研修
① 信者・来参者・職員などに対して「緊急防疫体制マニュアル」の周知を図ること。
② 信者・来参者・職員などに対して「緊急防疫体制マニュアル」に基づいた訓練を行うこと。
③ ①②の基づき「緊急防疫体制マニュアル」の検証や修正などを継続的に行うこと。
⑷ 宗教団体の防疫行動
① 宗教団体においては、防疫行動の第一に、宗教主宰者の明確な意思決定が必要です。
② この意思決定とその表明は、「一分一秒を争う」という認識で、可及的速やかになされることが必要です。
③ 仮に「空振り」があったとしても咎められることではなく、「英断」「勇断」出あったと考えるべきです。
④ 第二に、「緊急防疫体制マニュアル」に基づいて、速やかに、指揮命令系統を明確にし、周知・徹底させることです。
⑤ その指揮命令系統に基づいて、速やかに、発症者の隔離、接触者の隔離、「非汚染エリアの設定」、施設内にある者に対する行動規制、施設の使用規制、施設の閉鎖などを行います。
⑥ 宗教団体における防疫行動は、「緊急時における行動」「非常の行動」であり、「当面の行動」でもあります。
⑦ 先のことは二の次にして、目下の当面のことに集中して行い、かつ、それで足りると考えられます。
⑸ 発症者の隔離など
① 宗教団体の中で発生した「感染症の発症者」は、権威ある診断・検査等の結果を受けてからではなく、それと「疑わしい」時点で、個室に隔離するのが適切です。
② その上で、救急要請(消防署)、医療機関・保健所・行政担当機関などに、速やかに連絡・通報します。
③ 発症者の隔離室の出入りは基本的に禁止して(または厳格に制限して)、医師・看護師・救急関係者・行政担当者らの到着を待つことになります。
④ 宗教団体でありがちな、発症者および関係者への面会要望・祈祷要望などは、当面は禁止とするべきです。
⑹ 接触者の隔離など
基本的に、「感染者の隔離」と同様に、またはに「感染者の隔離」に準じて、「接触者の隔離」も実行します。
⑺ 信者・来参者・職員などの行動規制
① 宗教団体においては、多数の信者や来参者があり、必ずしも、指揮命令系統通りには行動規制が取れないいなみがあります。
② その意味で、少数の職員が、マニュアルを熟知した上で、一人一人が迅速かつ的確に行動を取る必要があります。
③ マニュアルの研修および平時における訓練が欠かせません。
⑻ 宗教施設の閉鎖
① 宗教団体において、万人の救済の施設である「宗教施設を閉鎖する」ことは、大きな決断を必要とすることです。
② 宗教主宰者の決断が重視される所以です。
③ 宗教施設の閉鎖は、「全施設の閉鎖」のみではなく、当然に、「一部の施設のみの閉鎖」があります。
④ ただし、「宗教施設の閉鎖」に慎重になるあまり、時期を失してしまわないように充分の注意が必要です。
⑼ 宗教団体における感染症予防体制の基本原則
① 第一に、信者・来参者・職員・宗教職などに感染症を罹患させない対応をすること。
② 第二に、宗教施設において、感染症の感染・伝播をさせない対応をすること。
③ 第三に、宗教団体として、感染症蔓延の原因とならない対応をすること。
⑽ 宗教活動の中止などと代替手段
① 宗教団体のあらゆる宗教活動においては、㋑多数の宗教職・信者らの一堂への集会・接触・交唱・読経・歌唱など、㋺宗教職・信者らの握手・抱擁・接吻・触手・按手などの濃厚接触、㋩宗教職・信者らの神酒・神饌・ミサ・聖餐・呈茶・共食などおよび朝食・昼食・夕食・夜食の共同飲食が予定されており、感染症の伝播が危惧されます。
② 宗教団体においては、各々の責任ある機関において、各宗教・各教宗派・各団体の教義・教理・伝統などを十分に(しかも、緊急に)検討した上で、その全部または一部の中止・延期・変更・縮小などの決定をして、これを公示し、可及的速やかに関係者に通知することが必要です。
③ 宗教団体において、最も重要な聖なる礼拝・供養・諸式などを中止・変更することは極めて困難でありますが、現状に関する正確な情報の入手に努め。事態の推移を見極めて、苦渋の決断を下すことも重要です。
④ 一方で、このような時にこそ、宗教団体に依存し、宗教施設に参詣・参拝し、神仏に礼拝・供養し、宗教職から特別の行為を頂き、特別の下賜を頂いて安心・平安・安寧を得たいとする信者や一般の方々も多数おられるのも事実です。
⑤ したがって、宗教団体としては、単に、宗教活動を中止したりするのみではなく、これらの不安を抱き、平安を得たいと願う信者や一般の方々のためにも、それぞれの教義・教理・伝統などに照らして、適性・妥当な代替手段を呈示し、実行することが重要です。
⑥ 宗教団体としては、それぞれの宗教の協議・教理・伝統などに照らして、同一空間に存して直接の参加ではなく、霊的な参加が可能であれば、インターネット、SNS、LINE、テレビ電話、DVD、CDなどの、電子手段・電気通信などによる提供を検討することが必要です。
・
3 費用負担
① 感染症防疫対策に要する費用は、基本的に、「宗教団体の負担」となります。
② 所定の対策は、Ⓐ「市町村の負担」、Ⓑ「都道府県の負担」、Ⓒ「国の負担」とされています。
③ 所定の対策については、「国の補助」があります。
・
4 特別措置
(「新型インフルエンザ等対策特別措置法」)
・
5 緊急事態措置
(「新型インフルエンザ等対策特別措置法」)
⑴ 緊急事態宣言
① 対策本部
① 新型インフルエンザ等が発生したとき、「対策本部」を設置。
② 対策本部の種類
・ ㋑ 「政府対策本部」
・ ㋺ 「 現地対策本部」
・ ㋩ 「 都道府県対策本部」
・ ㋥ 「 市区町村対策本部」
③ 本部長
・ ㋑ 政府対策本部長 = 内閣総理大臣
・ ㋺ 都道府県対策本部長=都道府県知事
・ ㋩ 市区町村対策本部長=市区町村長
② 「緊急事態宣言」
① 緊急事態宣言
・ 政府対策本部長(首相)は、新型インフルエンザ等が国内で発生し、全国的・急速な蔓延により、国民生活・国民経済に甚大な影響を及ぼす事態が発生したとき、「新型コロナウイルス等緊急事態宣言」をします。
② 緊急事態宣言の内容
・ ㋑ 実施期間(二年以内)
・ ㋺ 実施区域
・ ㋩ 緊急事態の概要
③ 新型インフルエンザ等対策の的確・迅速な実施に必要な措置
⑵ 蔓延防止措置
① 蔓延防止措置
・ 特定都道府県知事は、蔓延防止措置を講じることができます。
② 住民に対して
・ 潜伏期間・治癒までの期間、居住場所などから外出しないことなどの要請をすることができます。
③ 施設管理者等に対して
・ ㋑ 施設管理者等
・ Ⓐ 下記㋩の施設の管理者
・ Ⓑ 下記㋩の施設を利用して催物を主催する者
・ ㋺ 施設使用制限等の要請
・ Ⓐ 施設の使用制限・使用停止などの要請
・ Ⓑ 催物の開催制限・開催停止などの要請
・ ㋩ 対象となる施設(多数の者が利用する一定の床面積のもの)
・ 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校
・ 保育所、介護老人保健施設など
・ 大学、専修学校、各種学校その他の教育施設
・ 劇場、観覧場、映画館、演芸場
・ 集会場、公会堂
・ 展示場
・ 百貨店・マーケットなど物品販売業の店舗
・ 集会の用に供するホテル・旅館の部分
・ 体育館、水泳場、ボーリング場などの運動施設・遊技場
・ キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホールそなどの遊興施設
・ 理髪店、質屋、貸衣装店などのサービス業の店舗
・ 自動車教習所、学習塾などの学習支援業の施設
・ ㋥ 対象外の施設
・ 神社、寺院、教会など宗教施設は、使用制限・使用停止などの対象外です。
・ ただし、上記㋩に該当する施設は、対象施設となります。
④ 臨時の医療施設のため
・ 土地・家屋・物資の使用
⑶ 生活・経済の安定措置
① 患者の権利利益の保全
② 金銭債務の支払い期限の延期
③ 医薬品等の譲渡の特例
⑷ 「信教の自由」
① 各種の措置・要請・指示などと「信教の自由」
② 患者などの「信教の自由」
⑸ 宗教団体の対応
① 対策本部・行政機関・医療機関などに協力
② 宗教団体独自の対応
・


XVI 危機管理規程
1 危機管理規程とは
⑴ 「危機管理」には「ルールが必要」
① 「危機管理」は、「異常な現象」「非常の状態」「緊急の事態」など、「平常でない事態」に対処・対応するものです。
② 「危機管理」は、「平常でない事態」に、迅速・的確に、対処・対応しなければなりません。
③ 非日常的な事態に、迅速・的確に、対処・対応するためには、あらかじめ「ルール」を定めておくことが必要です。
⑵ 危機管理の組織
①
②
③
⑶ 危機管理の施設・設備・用品
①
②
②
⑷ 危機管理の協定
①
②
③
⑸ 危機管理の規程
①
②
②
2 危機管理協定
⑴
①
②
③
⑵
①
②
②
3 危機管理規程
⑴
①
②
③
⑵
①
②
②
(長崎県五島の漁港)
XVII HACCP(危害分析重要管理ポイント)
1 食品の危機管理
⑴ 食品衛生法
㋑ 第51条第1項 厚生労働大臣は、食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための取組みに関する基準を定める。
㋺ 第51条第2項 営業者は、前項の基準に従い、公衆衛生上必要な措置を定め、遵守しなければならない。
㋩ 第51条第3項 都道府県知事・保健所設置市長・特別区長は、公衆衛生上必要な措置について、第1項の基準に反しない限り、条例で必要な規定を定めることができる。
㋥ 東京都・食品衛生法施行条例。
⑵ 「HACCP」とは
① Hazard(ハザード、危害、危害要因)
② Analysis(分析)
③ Critical(決定的、重大な、危機的、限界)
④ Control(コントロール、管理)
⑤ Point(点、ポイント)
⑶ 「HACCP」とは
㋑ 「ハサップ」。
㋺ 危害要因を分析する重要管理ポイント。
㋩ 「危害分析重要管理ポイント」「危害分析重要管理点」。
㋥ 食品に関する事故を事前に防止するための衛生管理システム。
⑷ 食品製造業・飲食店・食品販売店
㋑ 米国FDA(食品医薬品局)のマニュアル。
㋺ 厚生労働省のパンフレット。
㋩ 厚生労働省『食品衛生管理の手引き』。
㋥ 食品衛生管理の見える化。
㋭ 令和2年(2021年)6月1日から、HACCP導入が義務化。
2 HACCP7原則
⑴ ハザード(危害要員)の分析
⑵ CCP(重要管理ポイント)の決定
⑶ 許容限界の決定
⑷ CCPのモニタリング手順の確立
⑸ 許容限界逸脱時の是正措置の設定
⑹ 検証手順の確立
⑺ 記録保存システムの確立
3 HACCP5手順
⑴ HACCP実施チームの編成
⑵ 仕様書・レシピなど(製品説明書)の作成
⑶ 意図する使用方法の確認
⑷ フローダイヤグラムの作成
㋑ 材料の受入れから製品の提供に至る一連の工程を一覧にする。
㋺ 一連の工程一覧図(フローダイヤグラム)を作成する。
㋩ 作業の手順書を作成する。
㋥ 作業を行う施設内の図面を作成する。
⑸ 現場の確認
㋑ 上記の一覧図・手順書・図面を現場で確認する。
㋺ 実際の作業工程、使用する用語・名称、設備、作業内容、機器の配置、人の流れ、材料・製品の流れなどと照合する。
㋩ 実際の作業内容を把握・確認する。
・
・